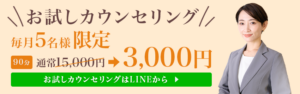「子どもの気持ちを尊重すること」はとても大切です。しかし、親としてどこまで関わるべきなのか、悩むことも多いのではないでしょうか?
「学校に行きたくない」と言われたとき、無理に行かせるべきなのか、見守るべきなのか、それとも子どもの判断に任せるべきなのか…。
最近では「不登校でもいい」「学校に行かなくても大丈夫」といった考え方も広がっていますが、実際にお子さんが不登校になると、どう対応すればいいのか分からず、不安を抱える親御さんも少なくありません。
また、「子どもの権利」が尊重される時代になり、学校に行かないという選択がある一方で、本当にそれでいいのか? と悩む声も増えています。
この記事では、子どもの権利とは何か、親の役割はどこまでなのか、不登校と子育てスタイルの関係について考えていきます。どう接するのが正しいのか分からず悩んでいる親御さんにとって、少しでもヒントになれば幸いです。
子どもの権利をどう考えるべきか?
「子どもの権利を尊重すること」は、とても大切なことです。しかし、その解釈が時に親御さんを悩ませることもあります。
日本の義務教育制度は、「親が子どもを学校に行かせる義務」と「子どもが学校に通う権利」 の両方で成り立っています。
では、「好きなように生きる」という子どもの権利 は、どこまで認められるべきなのでしょうか?
- 学校に行かない選択も、子ども自身が決めるべきなのか?
- 不登校になったとき、親はどう関わるのが最善なのか?
「不登校でもいい」「学校に行かなくても大丈夫」という考え方が広がりつつありますが、
実際には、学校に通うことは、子どもにとって社会とつながる重要な機会 でもあります。
そして、それを実現することは 親の大切な役割 でもあるのです。
また、現代では「ハラスメント」の概念が広がり、学校だけでなく家庭においても、「しつけ」と「過度な干渉」の境界が曖昧になっている ことも、不登校問題に影響を与えていると言われています。
子育てには4つのスタイルがある
アメリカの心理学の研究では、親の関わり方によって4つの子育てスタイル に分類されると報告されています。
- 独裁的なスタイル(厳しく管理し、親のルールを優先)
- 受け身型のスタイル(甘やかしすぎ、親が子どもに従う)
- 無関心型(ネグレクト)(放任し、関心を示さない)
- 民主的なスタイル(適切なルールを決め、子どもを尊重しながら育てる)
この中で、最も不適切とされるのは「ネグレクト型」 ですが、次に不適切とされるのが 「受け身型のスタイル」 です。
不登校に多い「受け身型の親子関係」とは?
不登校に関する相談の多くが、「受け身型の親子関係」 に該当するケースです。
なぜ「受け身型」の子育てが問題なのか?
- 過保護になり、子どもが親に頼りすぎてしまう
- 親子関係が逆転し、子どもが親よりも優位に立ってしまう
- 学校や家庭以外でトラブルがあった際に、頼れる人がいなくなる
- 「嫌なことがあったら逃げればいい」と思い、適応力が育たない
このような環境では、子どもが「学校が合わない」と感じたとき、
新しい環境に適応する力が育ちにくくなる ため、不登校が長引く原因になってしまうことがあります。
「民主的な子育て」で育った子どもの特徴
一方、「民主的な子育てスタイル」 で育った子どもは、
- 自立心が高く、不安が少ない
- 落ち込みにくく、回復力がある(レジリエンス)
- 社会性が身につき、対人関係がスムーズ
- 自分の能力に自信を持ちやすい
といった特長があると言われています。
したがって、親御さんが 「適切な距離感で見守ること」 が、子どもの健やかな成長にとって重要なポイントとなります。
子どもの権利を尊重しながら、適切な指導を
「子どもの気持ちを尊重すること」と「親が関わること」のバランスを取るのは難しいですが、
- ルールを決めること
- 適切な指導をすること
- 必要なサポートをすること
は、決して「子どもの自由を奪うこと」ではありません。
不登校の問題を解決するには、親子の関係性を見直し、適切な子育てスタイルを築くこと が大切です。
「どう接すればいいのか分からない」「このままでいいのか不安…」そんなときは、一人で抱え込まずに、専門家に相談することも一つの方法です。