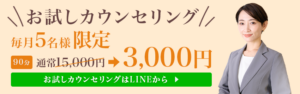「学校に行きたくない…」
お子さんがそう言い出したとき、親御さんはどう対応すればいいのでしょうか?
近年、不登校の子どもの数は増加傾向にあり、特にコロナ禍をきっかけにその問題が深刻化しています。
「無理に学校へ行かせるべき? それとも見守るべき?」このように悩む親御さんは少なくありません。
最近では「不登校でもいい」「学校に行かなくても大丈夫」という考え方も広がりつつありますが、
実際に不登校になると 子どもだけでなく、親御さん自身も大きな不安を抱える ことになります。
本記事では、不登校の現状や原因、家庭への影響、そして親としてできること について詳しく解説していきます。「どう対応すればいいのか分からない」と感じている方にとって、少しでもヒントになれば幸いです。
不登校の現状と主な原因
近年、不登校の問題はますます深刻化しています。特に、コロナ禍の影響を受け、不登校の子どもの数は増加傾向 にあります。
文部科学省の調査によると、不登校の主な原因には、以下のようなものが挙げられます。
- 無気力や不安 … 学校に行く意味を見出せず、気持ちが沈んでしまう
- 生活リズムの乱れ … 昼夜逆転や睡眠不足が学習意欲を低下させる
- 友人関係の問題 … いじめや孤立感から登校が難しくなる
- 親子関係の課題 … 家庭内でのストレスが積み重なり、対話が減る
- 学業の不振 … 授業についていけず、自信を失ってしまう
最近では、「不登校でもいい」「学校に行かなくても大丈夫」という意見も増えてきました。
しかし、実際に子どもが不登校になると、親御さんは日々悩み、苦しむことになります。
不登校がもたらす家庭の変化
不登校が続くと、家庭内にもさまざまな影響が出てきます。
- 生活習慣の乱れ … 夜型生活になり、朝起きられなくなる
- 親子のコミュニケーションの減少 … 会話が減り、家庭内がぎくしゃくする
- 暴言・暴力の問題 … 感情をコントロールできず、親にあたることも
- デジタル機器の依存 … ゲームやSNSに没頭し、現実世界との関わりが薄れる
一方で、保護者の意識にも変化 が見られています。以前は「何がなんでも学校に行かせるべき」と考える親御さんが多かったのですが、最近では「無理に行かせなくてもいいのでは」と考えるケースも増えています。
しかし、「不登校を受け入れること」と「何もしないこと」は違います。
どう対応すればいいのか分からず、専門機関に相談しても 「見守りましょう」「待ちましょう」 と言われるばかりで、具体的な解決策が見つからず困惑する親御さんも少なくありません。
日本と海外の不登校対策の違い
アメリカなどでは、不登校の子どもに対して 認知行動療法(CBT) などの積極的な介入が行われることがあります。一方、日本では 「子どもの気持ちを尊重しながら、成長を待つ」 という比較的穏やかなアプローチが主流です。
また、日本では 義務教育中にまったく学校に行かなくても、高校受験が可能 という制度もあり、不登校の選択肢が広がっています。しかし、制度が整ってきたとはいえ、親御さん自身がどう向き合うか が、子どもの将来に大きな影響を与えることは変わりません。
親の安定が、子どもを支えるカギになる
不登校の子どもを支えるためには、まず親御さん自身が落ち着き、安定した心で子どもと向き合うこと が大切です。
- 焦らず、子どもとの関係を大切にする
- 必要に応じて、専門家のアドバイスを受ける
- 子どもの変化を見守りながら、粘り強く対応する
最近では、学校復帰率が上昇傾向にあります。
これは、家庭内での対応が変わることで、子どもにも変化が生まれている証拠 なのかもしれません。
「不登校の解決方法はひとつではない」
それぞれの子どもに合った対応を見つけ、親子で少しずつ前に進むことが、不登校からの回復への第一歩となります。
まとめ
- 不登校はコロナ禍の影響もあり、増加傾向にある
- 原因は 「無気力」「生活リズムの乱れ」「人間関係の問題」 などさまざま
- 日本では「見守る」アプローチが主流だが、海外では積極的な介入も行われている
- 親が落ち着いて子どもに向き合うことで、子どもの回復につながる
「何をすればいいのか分からない」 そんなときは、専門家に相談しながら、一歩ずつ前に進んでみませんか?