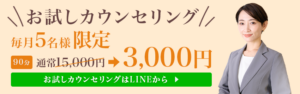不登校やひきこもりが続くと、学校に行かないことだけが問題ではなく、生活習慣の乱れや新たな課題が生じることがあります。
「お風呂に入らない」「歯を磨かない」「昼夜逆転が続く」こうした生活の変化に、親御さんはどのように対応すればよいのでしょうか?
子ども自身も「このままではいけない」と分かっていても、気力が伴わずに行動に移せないことがあります。
無理に改善させようとすると逆効果になってしまうこともあり、親としての関わり方が重要になります。
この記事では、不登校による生活の変化と、その対応方法 について詳しく解説します。
親御さんが少しでも安心して向き合えるよう、ヒントになれば幸いです。
不登校が続くと、生活習慣が乱れることも
不登校やひきこもりが長引くと、1日のほとんどの時間を家で過ごすようになり、新たな問題が発生することがあります。
身だしなみや衛生面の変化
家族以外の人と関わる機会が減ることで、身だしなみに気を使わなくなることが増えます。
その結果、次のような状態になることがあります。
- 何日もお風呂に入らない
- 歯を磨かない
- 服を着替えない
子ども自身も「このままではよくない」と感じていても、気力が伴わずに行動できない場合があります。無理に強制するのではなく、自主的に行動できるようになるまで見守ること が大切です。
外出の予定ができると、自然に改善することが多い ため、無理に急かさず、少しずつ変化を促していきましょう。ただし、身体の不調が見られる場合は、医療機関を受診することも検討 してください。
昼夜逆転が起こる理由とは?
不登校が続くと、昼夜逆転の生活になる子どもも少なくありません。この問題を改善するには、昼夜逆転が起こる背景や理由を理解すること が大切です。
子どもの立場になって考えると、昼夜逆転には次のような心理的要因があることが分かります。
① 罪悪感を避けるため
日中は、ほかの子どもたちが学校で勉強している時間です。この時間に起きていると、
「みんなは学校に行けているのに、自分は行けていない…」
という罪悪感を抱いてしまい、つらくなってしまうことがあります。そこで、あえて昼間は寝て、夜に活動することで気持ちを落ち着かせようとするのです。
② 家族と顔を合わせるのが気まずい
リビングに家族がいると、「親になにか言われるのではないか…」と不安になり、部屋から出にくくなることがあります。また、家族と顔を合わせるのが気まずく、夜中に活動することで「誰にも干渉されない安心感」 を求めることもあります。
昼夜逆転を解決するために親ができること
親としては、昼夜逆転を改善すれば学校に行けるようになるのでは…と考え、「早く寝なさい」「朝起きなさい」と強制してしまいがち です。
しかし、無理に生活リズムを戻そうとすると、かえって逆効果になることもあります。
子どもが自分から動けるようになるためには、「目的」を持たせること が大切です。
- 「毎日決まった時間にペットの散歩をしよう」
- 「○○に行ってみよう」
- 「夕方になったら一緒に買い物に行こう」
このように、生活リズムを整えるための「きっかけ」を作ると、子ども自身が無理なく動けるようになり、少しずつ改善されていく ことが多くあります。
病気が隠れている可能性も
ただし、昼夜逆転の背景には、身体の不調や心の問題 が潜んでいることもあります。
- 起立性調節障害(朝起きられない、めまいや立ちくらみがある)
- うつ症状(気分が落ち込み、何もやる気が起きない)
このような症状がある場合は、生活習慣の問題だけではなく、医療機関に相談することも大切 です。
まとめ
不登校やひきこもりが続くと、生活習慣の乱れが起こりやすくなります。
- 身だしなみや衛生面の変化(お風呂に入らない、歯を磨かない など)
- 昼夜逆転の生活(罪悪感や家族との関係から昼夜逆転になることも)
- 親が無理に正そうとすると逆効果になることがある
- 「目的」を持たせることで、自然に改善するケースが多い
- 起立性調節障害や心の病気が背景にある場合は、医療機関に相談することも大切
「どうすれば生活リズムが整うのか」と悩んでいる親御さんも多いかと思いますが、無理に変えようとせず、子どもが少しずつ動き出せるきっかけを作ること を意識してみてください。